・・・ルキアが熱にうなされたまま、睦月の十四日は過ぎていった。
今年は何を贈ろうか、そのようなことを考える余裕さえ、今年は無かった。
先日の侍医からの言葉が、私の肩に重く圧し掛かる。
そう、今日くらいまでに熱が下がらなければ・・・
・・・お前まで、まさか、私の目の前からいなくなるのか?・・・
私らしくも無い考えが浮かんでは、消えることなく頭から離れなかった。
私にはもはや・・・願い、祈ることしか出来なかった。
―・・・私を置いて逝ってくれるな。
―・・・私に再び与えられた光を、容易く奪い去ってくれるな。
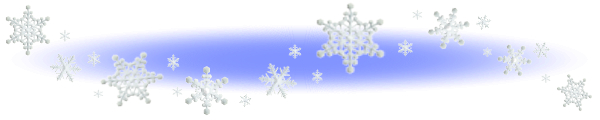
睦月の十七日。
あれから病の峠を越し、ようやく熱も下がったルキアは、久々に復帰することが許された。
ずっと隊に迷惑を掛けていたので頑張らねば、とルキアは意気込んでいる。
・・・まだ完全ではないというのに。
この娘が心配でならない私の心のうちなど、当の本人には恐らく分かるまい。
とはいえ、久々のルキアの復帰である。
死神であることを誇りに感じているこの娘が、再び死神として復帰できることが嬉しくないわけがなかろう。
そして何より、病の後遺症も無く回復してくれたことに、私は何よりも安堵し、
またルキアの心のうちが手に取るように分かるせいか、私まで少し高揚していた。
・・・この気持ちを、どうすれば収められるのだろうか。
-そういえば、ルキアの誕生日を祝っておらぬ。
この高揚した思いを、あの娘の祝いに費やす・・・そう、思いついた。
あの娘のために冷静さを欠いているのなら、あの娘のことで高揚を解き放てば、
再び冷静になれるやもしれぬ、そう単純に思ったのだ。
・・・勿論、それはただのこじつけであり、実際は冷静になど、なれるわけがない。
結局は、私がそうしたい、故に、そうする、只それだけなのだ。
睦月の二十一日。
ルキアの復帰の日は、明日・・・睦月の二十二日である。
復帰が決まってから、快気と復帰の祝いと合わせて、この日にルキアの誕生祝をしよう、
と・・・数日前から己の内で決めていた。
あの娘は自分を卑下するくせがある・・・
恐らく、隊に無事に復帰する以前に自分のことを祝われたところで、
半人前の私には恐れ多いだの、力不足の私には祝われる資格がないだのといって、祝いを拒絶するだろう。
何よりも、ルキアが完全に本調子に戻るまでは、己自身、心から安堵して誕生日など祝えまい、そう思っていた。
病によりルキアが死線をさまよっていた事は、変えようも無い事実なのだ。
しかしながら、私の誕生日に近くなれば、そちらのほうにルキア自身だけでなく清家や他の従者らも
意識が向き、ルキアを蔑ろにするのではないか、という懸念も存在した。
・・・出来るだけ状況の許す限り早く、という思いも、心の内に在った。