睦月二十二日 4
すや・・・と、規則正しいルキアの寝息が聞こえてきた。
中々寝付けぬ私は、体を起こして・・・眠るルキアを見下ろしていた。
柔らかな月の光が、障子を通して、部屋をかすかにではあるが、明るく照らす。
その光に、ルキアの眠る顔が照らされ、白く浮き上がる。
・・・それは暗がりになれた私の目には、眩しいくらいだった。
この娘が助かるようにと、数日前までは只管に願っていた。
漸く熱が下がり始めた時、そして後遺症も何も無いと報告を受けたとき、
思わずその場に崩れてしまうのではないかと思うくらいの安堵を感じた。
だが一方で、
この・・・隣りで穏やかに眠っている娘を、かつて私は見殺しにした。
それどころか、自らを縛る『掟』を振りかざして、この手に掛けようとさえした。
護るべきこの娘の命を、自分の手で奪おうとさえしたのだ。
寂しさや孤独を与えただけでは、私は、無かった・・・。
・・・この娘に、私はどれ程の恐怖を与えたのだろうか。
本来であれば、いざとなれば自分を一番護ってくれるだろうはずの家族に見捨てられ、
それどころかその家族自ら、自分を殺しに掛かるのだから。
「・・・さぞや・・・怖かったろう・・・辛かったろう・・・・」
この家に引き取られて以来、この娘は必死になじもうとしていた。
・・・私に捨てられぬようにと。捨てるわけなど無いにも拘わらず。
とはいえ・・・お前の処刑を伝えたとき、あれは、確かに・・・
私は、一度、お前を捨てたに・・・等しい。
そして、あの時・・・自分の心も、捨てたに等しい。
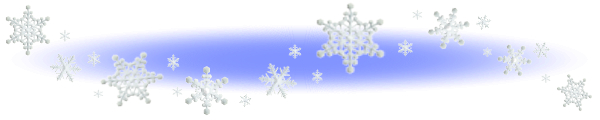
お前が先日の病に罹ったときでさえ、私はお前が助かるようにと
一心不乱に願い、祈っていたのに、
何故、お前の処刑については、あれ程までに悩んだのだろうか。
そして、悩んだ末に、お前を見捨てることを決めたのか・・・。
にもかかわらず、私は半ば自棄になってもなお、もがいていたな。
仕方ないのだ、無駄な足掻きは止めて諦めろ、と己に言い聞かせながら。
―・・・悩むくらいであれば、最後は己の内の意思のままに、か。
刃を交えたあの小僧の迷いの無い一太刀に、私は敗れた。
確かに、私の意思は、私の本当の意思は、あの時・・・
振り下ろした刃の中に、無かったのやもしれぬ。
罪人とされたルキアをこの手に掛ける、という表面上の意思の下に、
本当にあった思いは・・・今なら分かる。
―・・・ルキアを、
・・・助けたい、救いたい・・・護りたい。
結果的には、私がこの娘を救うことに何の障壁も無くなった。
それでも、もしもあの時・・・未だにルキアを護ることに対する『掟』という名の障壁があったなら、
私は・・・この娘を庇って刃を受けることが出来ただろうか?
いや、問うだけ無駄であろう、歴史に『もしも』を問うてはならぬ、という。
障壁は消えた・・・あれはあれで、事実なのだ。
それに、敢えて問うても答えは明らか。
―・・・是、だ。
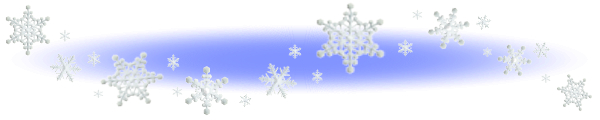
ならば、何故・・・私は、
この娘を孤独の中に放り込んだままにしたのだ?
この娘の誇りを踏みにじるような真似をしたのだ?
この娘に死ぬよりも辛い恐怖を与えるような真似をしたのだ?
この手に伝わる温もりを、何よりも変えがたい存在を、失うやもしれぬような真似が、出来たのか・・・・
もっと早く、この娘を掬い上げることをしなかったのか・・・・
もっと早く、私の内なる意思に従わなかったのか・・・・